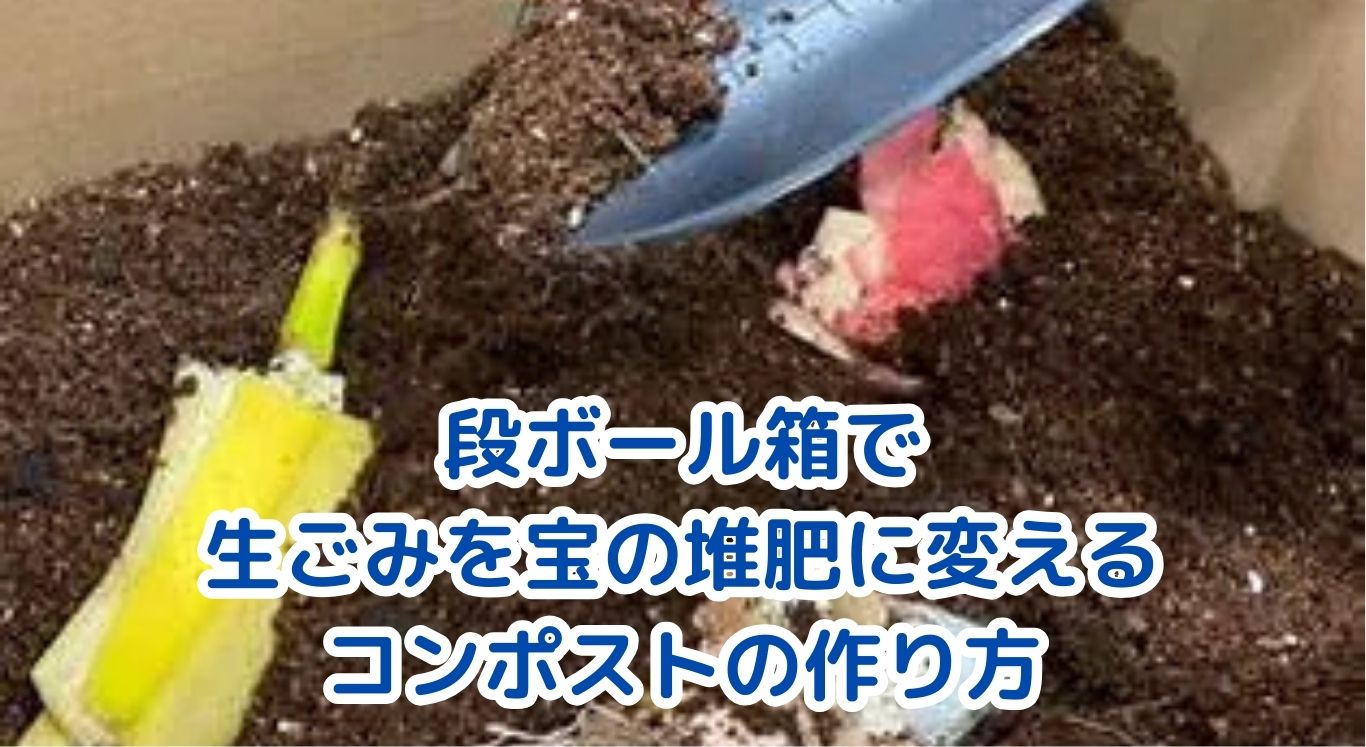皆さん、こんにちは!毎日の生活で出る生ごみ、捨てるだけではもったいないと思ったことはありませんか?今日は、そんな生ごみを宝の堆肥に変える「段ボールコンポストの作り方」をご紹介します!
段ボール箱と少しの材料で、誰でも簡単に始められるエコな取り組みなんです。家にある段ボール箱を再利用して、生ごみを資源に変えられます。


ただし、何も知らずに始めると失敗してしまうこともあるので、基本的なポイントを押さえておくことが大切です。この記事では、初心者の方でも失敗しない段ボールコンポストの作り方から、上手に続けるコツまで、分かりやすくご説明します。
生ごみが減って環境にも優しく、できた堆肥で植物を育てる喜びも味わえる一石二鳥の取り組み。一緒に始めてみませんか?
この記事のポイント
- 段ボール箱で簡単に作れる生ごみ処理方法
- 必要な材料と組み立て手順
- 基材の作り方と管理方法
- よくある失敗と対策法
引用:名古屋市:段ボールコンポストによる堆肥の作り方・使い方(暮らしの情報)
段ボールで作る家庭用コンポストの基本的な作り方

必要な材料と道具の準備


段ボールコンポストを作るには、まず必要な材料と道具を集めることから始めましょう。家にあるものでも簡単に作れるので、特別なものを買う必要はありません。
まずは段ボール箱を用意しましょう。みかん箱くらいの大きさで、厚めの段ボールが理想的です。底を金具で止めたものだと丈夫で長持ちしますよ。段ボールは通気性(つうきせい:空気が通る性質)がよく、生ごみの水分を逃がしたり、発酵に必要な空気を通すのに適しています。
次に必要な材料と道具をまとめると、こんな感じです:
| 必要な材料 | 必要な道具 |
|---|---|
| 段ボール箱 | スコップ(小さいものでOK) |
| 新聞紙(2日分程度) | ガムテープ |
| 腐葉土(ふようど) | ゴム手袋 |
| 米ぬか | 温度計(あれば便利) |
| 風呂敷や古いTシャツなどの布 | |
| ひもかゴム | |
| ブロックやすのこなどの台 |


腐葉土と米ぬかは基材(きざい)と呼ばれ、微生物のすみかと栄養になります。腐葉土はホームセンターや園芸店で、米ぬかは精米所で手に入れることができます。
また、段ボール箱の底の風通しをよくするために、ブロックやビール瓶ケース、すのこなどの台も必要です。これらを置いて、その上に段ボール箱を置くことで、底から空気が入るようになります。
これらの材料と道具が揃ったら、いよいよ段ボールコンポストづくりに挑戦できますね。シンプルな材料で環境にやさしい取り組みができるのは素晴らしいことです。
初心者でも失敗しない組み立て手順
段ボールコンポストの組み立ては、順番に従えば誰でも簡単にできます。
ここでは失敗しないポイントを押さえながら、手順を説明していきましょう。
まず、段ボール箱をひっくり返して、底面をガムテープでしっかり止めます。
虫が入らないように、箱の隙間や穴もガムテープでふさぎましょう。
これは虫が発生する原因を防ぐ大切なステップです。
次に、箱の底が抜けないように補強します。
底に別の段ボール板を敷いて二重にすると丈夫になります。
その上に新聞紙を2日分程度敷きます。
新聞紙は水分を吸収する役割があります。
基材を入れる準備ができたら、次の手順で進めていきましょう:
1.腐葉土と米ぬかを重さ5対3の割合で箱に入れ、よく混ぜます
2.ブロックなどの台の上に段ボール箱を置きます
3.風通しがよく、雨があたらない場所を選びます
4.布などをかけて、虫が入らないようにひもやゴムで止めます
段ボール箱を置く場所は、壁から5cm以上離すと通気性がよくなります。
また、直射日光が当たらない場所が理想的です。
夏は涼しい場所、冬は暖かい場所に置くと微生物が活発に働きます。
このように組み立てれば、基本的な段ボールコンポストの完成です。
シンプルな構造ですが、微生物の力を借りて生ごみを資源に変える素晴らしい仕組みになっています。
初めての方でも、この手順に従えば失敗することはないでしょう。
米ぬかを使った基材の作り方
段ボールコンポストの心臓部とも言えるのが基材です。
基材とは微生物が住み、活動する場所のことで、その作り方がコンポストの成功を左右します。
特に米ぬかは微生物の栄養となり、発酵を促進する重要な役割を果たします。
基材の基本的な配合は、腐葉土と米ぬかを重さで5対3の割合で混ぜるのがベストです。
例えば、腐葉土3.5kgに対して米ぬか2.1kgを使うとちょうどよい量になります。
これらをしっかり混ぜ合わせることで、微生物が活動しやすい環境が整います。
米ぬかの役割は主に次の3つです:
1.微生物の栄養源になる
2.発酵を促進する
3.生ごみの分解を早める
基材を作る際のポイントとして、水分量の調整があります。
理想的な水分量は、握るとかたまりになり、つつくと崩れる程度です。
乾燥しすぎている場合は、米のとぎ汁や水を少し足すとよいでしょう。
逆に水分が多すぎる場合は、基材や米ぬかを追加して調整します。
また、生ごみを入れるたびに米ぬかをひとつかみ加えると、発酵がより活発になります。
特に温度が上がらない場合は、コップ1杯程度の米ぬかを追加すると効果的です。
基材の状態は定期的に確認することが大切です。
温度が30度~60度くらいに上昇していれば、微生物が活発に活動している証拠ですね。
温度が上がらない場合は、使用済みてんぷら油を100ml程度加えるのも一つの方法です。
このように米ぬかを活用した基材づくりは、段ボールコンポストの成功に欠かせません。
微生物の力を最大限に引き出し、生ごみを効率よく分解する環境を整えましょう。
コーヒーかすを活用する方法
コーヒーを飲んだ後に残るコーヒーかすは、実は段ボールコンポストの強い味方です。
捨ててしまうのはもったいない、貴重な資源なのです。
コーヒーかすがコンポストに向いている理由はいくつかあります。
まず、水分を適度に含んでいるため、そのまま使えます。
また、細かく挽いてあるので分解しやすく、臭いや虫が発生しにくいという特徴があります。
さらに、消臭効果があるので、コンポストの臭い対策にも役立ちます。
コーヒーかすを段ボールコンポストに活用する方法は簡単です:
1.水分を切らずにそのままコンポストに入れる
2.基材とよく混ぜ合わせる
3.定期的にかき混ぜて空気を送り込む
ただし、コーヒーかすだけでは微生物の栄養が足りないため、米ぬかなどの発酵促進材と一緒に使うとよいでしょう。
発酵促進材の例としては、ヨーグルト液(ヨーグルトを食べ終わった後の容器に水を入れたもの)や納豆液(納豆を食べ終わった後の容器に水を入れたもの)などがあります。
コーヒーかすを入れる際の注意点もあります。
コーヒーに含まれるカフェインが植物の生長を阻害する恐れがあるため、必ず充分に発酵させてから堆肥として使用してください。
発酵不良の未熟堆肥は植物に害を与える可能性があります。
完成したコーヒーかす堆肥の使い方は、鉢植えやプランターの場合は土の2~3割程度混ぜて使用します。
地植えの場合は、根を傷つけない程度の穴を掘って埋めるとよいでしょう。
このようにコーヒーかすを活用することで、ごみの減量だけでなく、良質な堆肥を作ることができます。
コーヒーを飲む習慣がある方は、ぜひ試してみてくださいね。
資源を循環させる素晴らしい取り組みになります。
段ボールコンポストを長持ちさせる管理方法

最適な置き場所の選び方


段ボールコンポストを始める際、まず悩むのが「どこに置くか」という問題です。適切な場所を選ぶことで、コンポストの効果を最大限に引き出せます。
具体的な置き場所として、以下のような選択肢があります:
| 置き場所 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|
| ベランダ | 家の中に臭いが広がらない | 雨よけ対策が必要 |
| 軒下 | 雨が当たりにくい | 風通しを確保する |
| キッチン | 生ごみをすぐ投入できる | 臭いが気になることも |
| 玄関 | 生活空間と分けられる | 来客時に見えないよう工夫を |
| カーポート | スペースを取らない | 直射日光を避ける |


どの場所を選ぶにしても、壁から5cm以上離して置くことで通気性が良くなります。また、段ボール箱の底が湿らないよう、必ずブロックやすのこなどの台の上に置きましょう。これは段ボールが水分を吸って崩れるのを防ぐためです。
冬場は微生物の活動が鈍くなるため、できるだけ暖かい場所に移動させるとよいでしょう。寒冷地では室内に取り込むことも検討してみてください。
小松市の実験によると、置き場所を適切に選ぶことで、生ごみの分解効率が大きく変わることが確認されています。あなたの生活スタイルに合った場所を見つけることが、長く続けるコツですね。
禁止食材と入れてはいけないもの
段ボールコンポストに何でも入れられるわけではありません。
微生物がうまく分解できないものや、悪臭・虫の原因になるものは避けるべきです。
入れてはいけないものを知らずに投入すると、せっかくのコンポストが失敗してしまう可能性があります。
以下のリストを参考にしてください:
入れてはいけないもの:
- 柑橘類の皮(みかん、レモンなど):酸性が強く発酵を妨げます
- 玉ねぎの外皮:抗菌作用があり分解されにくいです
- 生肉・生魚:強い臭いの原因になります
- 貝殻・骨:分解されにくく、堆肥作りの邪魔になります
- トウモロコシの芯・タケノコの皮:繊維質が多く分解に時間がかかります
- 塩分の多い食品(漬物など):微生物の活動を阻害します
- 落ち葉・木の枝:虫や卵が付いている可能性があります
一方で、次のものは積極的に入れると良いでしょう:
入れると良いもの:
- 野菜くず(水切りしたもの)
- 果物の皮(柑橘類以外)
- コーヒーかす・茶殻(消臭効果もあります)
- 炭水化物(パン・ご飯など)
- 使用済みの天ぷら油(少量)
- 米ぬか(発酵を促進します)
名古屋市の資源循環推進課によると、生ごみは1日につき500〜800g程度を目安に投入するのが適量とされています。
量が多すぎると分解が追いつかず、臭いの原因になることもあるため注意しましょう。
これらのルールを守ることで、快適に段ボールコンポストを続けられますよ。
虫が発生したときの対策法
段ボールコンポストを使っていると、時に虫が発生することがあります。
これは自然の営みの一部ですが、あまり歓迎したいものではないですよね。
虫が発生する主な原因は、「隙間からの侵入」「生ごみに既に卵が付いていた」「水分過多」などです。
これらを防ぐための対策と、もし発生してしまった場合の対処法を紹介します。
予防策:
1.段ボールの隙間をガムテープでしっかり塞ぐ
2.布やネットで上部を覆い、虫が入れないようにする
3.生ごみは新鮮なうちに投入する(放置した生ごみには既に卵が産み付けられている可能性があります)
4.毎日かき混ぜて空気を入れ、発酵温度を上げる(40〜60℃が理想的)
もし虫が発生してしまった場合は、次の方法で対処しましょう:
対処法:
1.コンポスト内の基材をビニール袋に移し、空気を抜いて密封する
2.2〜3日間天日干しする(高温と酸欠で虫は死滅します)
3.再び段ボールに戻して使用を再開する
特に夏場は虫が発生しやすいため、注意が必要です。
白カビが発生した場合は心配無用です。
これは分解が順調に進んでいる証拠なので、そのままかき混ぜて使い続けましょう。
NPO法人循環生活研究所の平由以子氏によると、虫の発生は初心者がよく経験するトラブルの一つですが、適切な対策を取れば十分に防げるとのことです。
虫が出たからといって諦めず、対策を講じて続けてみてください。
基材の代用品と選び方のコツ
段ボールコンポストの基材は、市販品だけでなく身近なもので代用できることをご存知でしょうか。
基材選びのコツを知れば、より経済的にコンポストを始められます。
一般的な基材の組み合わせは「ピートモスとくん炭」や「腐葉土と米ぬか」ですが、これらは以下のようなもので代用可能です:
基材の代用品リスト:
- おがくず(木工所などで入手可能)
- 落ち葉(乾燥させたもの)
- 竹パウダー
- コーヒーかす(毎日少しずつ加えると効果的)
- もみ殻
- 山の腐葉土
- 剪定チップ
基材を選ぶ際のポイントは、「水分調整能力」と「通気性」のバランスです。
理想的な配合比率は、例えば腐葉土と米ぬかなら重さで5対3の割合が効果的です。
基材の水分量は非常に重要で、握ると固まり、指で突くとポロポロと崩れる程度が理想的です。
乾燥している場合は米のとぎ汁や水を少し足し、水分が多すぎる場合は基材を追加して調整しましょう。
また、基材の状態を確認する簡単な方法として、温度チェックがあります。
発酵が順調に進んでいれば、内部の温度は30〜60℃まで上昇します。
温度が上がらない場合は、コップ1杯程度の米ぬかを追加すると効果的です。
稲沢市の実験では、コーヒーかすを継続的に加えることで基材の交換頻度が減り、長期間使用できることが確認されています。
日々のちょっとした工夫で、基材の寿命を延ばすことができるのです。
初めての方は市販の基材から始め、慣れてきたら身近なもので代用してみるのも楽しいですね。
失敗しないための注意点
段ボールコンポストは比較的簡単に始められますが、いくつかのポイントを押さえておくと失敗を防げます。
初心者がよく陥る失敗とその対策をご紹介します。
よくある失敗と対策:
1.臭いが発生する
- 原因:空気不足、水分過多、生魚・肉の投入過多
- 対策:毎日かき混ぜる、水切りを徹底する、コーヒーかすを入れる
2.分解が進まない
- 原因:カロリー不足、水分不足、かき混ぜ不足
- 対策:廃食用油や米ぬかを追加する、適度な水分を保つ、毎日かき混ぜる
3.水分過多でべとべとになる
- 原因:生ごみの水切り不足、雨に濡れた
- 対策:基材を追加する、蓋を開けて水分を蒸発させる
4.虫が発生する
- 原因:隙間からの侵入、放置した生ごみの投入
- 対策:段ボールの隙間をテープで塞ぐ、防虫ネットを被せる
5.段ボールが壊れる
- 原因:水分過多、直接床に置いている
- 対策:台の上に置く、水分管理を徹底する
特に初心者が注意すべきは「毎日のかき混ぜ」です。
これを怠ると酸素不足になり、悪臭の原因になります。
生ごみを入れない日も、スコップで底からしっかりかき混ぜましょう。
また、季節によって対策を変えることも重要です。
冬場は微生物の活動が鈍るため、廃食用油や米ぬかを定期的に入れたり、お湯を入れたペットボトルを基材に入れるなどの工夫が効果的です。
岐阜市の公式ホームページによると、段ボールコンポストの寿命は約2〜3ヶ月とされています。
使用期間が長くなり、基材がべたついてかき混ぜにくくなったら、新しく始め直す時期です。
失敗を恐れず、試行錯誤しながら自分なりのコツを見つけていくことが大切です。
小さな成功体験を積み重ねて、楽しみながら続けていきましょう。
引用:名古屋市:段ボールコンポストによる堆肥の作り方・使い方(暮らしの情報)
家庭で簡単!段ボールコンポストの作り方と失敗しないコツ:まとめ
Q&Aでまとめますね。
質問(Q):
段ボールコンポストに必要な材料は何ですか?
回答(A):
段ボール箱、新聞紙、腐葉土、米ぬか、布、ひも、台(ブロックやすのこ)、スコップが必要です。
質問(Q):
段ボールコンポストの組み立て手順を教えてください。
回答(A):
底面をガムテープで固定し、二重底にして新聞紙を敷き、基材を入れ、台の上に置いて布で覆います。
質問(Q):
基材の正しい作り方は?
回答(A):
腐葉土と米ぬかを重さで5対3の割合で混ぜ、握ると固まり、つつくと崩れる程度の水分量に調整します。
質問(Q):
コーヒーかすはどのように活用できますか?
回答(A):
水分を切らずそのまま投入し、消臭効果があり、米ぬかなどと一緒に使うと効果的です。
質問(Q):
最適な置き場所の条件は何ですか?
回答(A):
雨が当たらず、風通しが良く、床から浮かせた場所で、壁から5cm以上離して置きます。
質問(Q):
コンポストに入れてはいけないものは何ですか?
回答(A):
柑橘類の皮、玉ねぎの外皮、生肉・生魚、貝殻・骨、繊維質の多いもの、塩分の多い食品は避けましょう。
質問(Q):
虫が発生したときの対策方法を教えてください。
回答(A):
基材をビニール袋に移して密封し、2〜3日間天日干しした後、再び使用を再開します。
質問(Q):
基材の代用品にはどんなものがありますか?
回答(A):
おがくず、乾燥させた落ち葉、竹パウダー、コーヒーかす、もみ殻などが代用できます。
質問(Q):
失敗しないためのポイントは何ですか?
回答(A):
毎日かき混ぜることが最も重要で、水分管理、適切な食材選び、季節に合わせた対策も必要です。
家庭から出る生ごみを資源として再利用できる素晴らしい方法をご紹介しました。シンプルな材料で始められ、環境にも優しい取り組みですよね。初めは少し手間に感じるかもしれませんが、コツをつかめば簡単に続けられますよ。ぜひご自宅でチャレンジしてみてください。微生物の力を借りて、生ごみが黒い土に変わっていく様子は、とても不思議で楽しい体験になるでしょう。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。