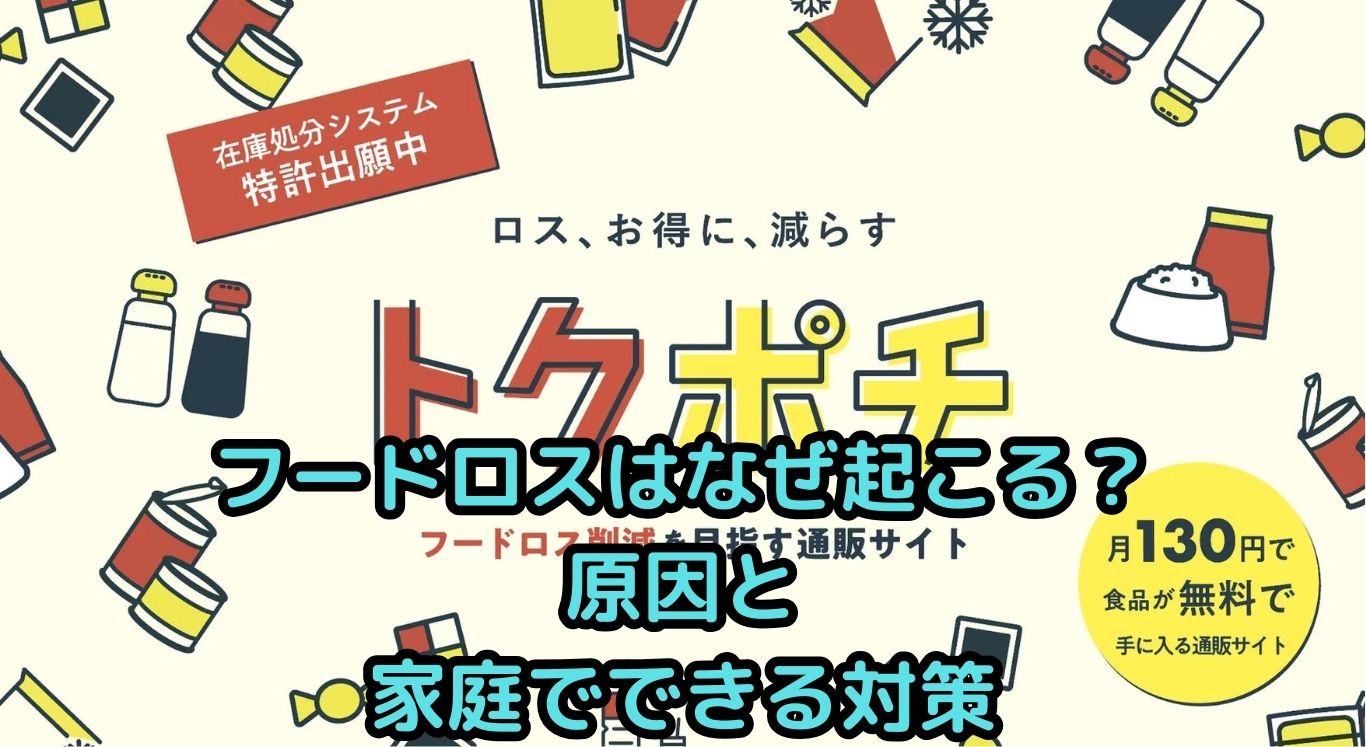「食べ物を無駄にしてはいけない」と分かっていても、なぜか発生してしまうフードロス。その背景には、私たちの生活習慣や社会の仕組みに根差した様々な原因が潜んでいます。
この記事では、フードロスがなぜ起こるのか、特に家庭で発生する原因に焦点を当てて詳しく解説します。さらに、今日からすぐに実践できる簡単なフードロス対策を5つ厳選してご紹介。「トクポチという通販サイトはあなたにもできるフードロス対策です。」という選択肢と合わせて、日々の暮らしの中で無理なく取り組めるヒントを見つけていきましょう。
フードロスが発生する主な原因:私たちの日常に潜む「もったいない」
フードロスは、食品が生産されてから消費されるまでの様々な段階で発生しますが、ここでは特に私たちの身近な「家庭」での発生原因と、その背景にある「事業者」側の要因を見ていきましょう。
家庭でフードロスが発生する原因
家庭から出るフードロスの内訳を見ると、主に以下の3つが挙げられます。
- 食べ残し:
- 作りすぎ: 家族の人数や食べる量を考慮せずに多く作りすぎてしまい、結果的に残してしまう。
- 好き嫌い: 特定の食材や料理が苦手で残してしまう。
- 体調不良など: 急な体調不良で食事がとれず、用意したものが無駄になる。
- 直接廃棄(手つかず食品):
- 買いすぎ: 安売りなどでつい多く購入し、使い切れないうちに賞味期限や消費期限が切れてしまう。
- 衝動買い: 献立を考えずに購入し、結局使わずに終わる。
- 冷蔵庫の奥で忘れられる: 購入したことを忘れ、気づいた時には期限切れ。
- もらいもの: 好みでなかったり、量が多すぎたりして消費しきれない。
- 賞味期限・消費期限の誤解: 賞味期限が切れただけで「もう食べられない」と判断し捨ててしまう。
- 過剰除去:
- 皮の厚むき: 野菜や果物の皮を厚くむきすぎて、食べられる部分まで捨ててしまう。
- 傷んだ部分の過度な除去: 少し傷んでいるだけで、まだ食べられる部分も一緒に大きく取り除いてしまう。
事業活動におけるフードロスの背景
家庭でのフードロスは、実は事業者の活動とも無関係ではありません。
- 過剰な品揃えと見た目の重視: スーパーなどでは、消費者の選択肢を増やすために多くの商品を並べますが、これが売れ残りリスクを高めます。また、少しでも見た目が悪い商品は敬遠されがちなため、規格外品として廃棄されることもあります。
- 販売期限の設定(3分の1ルールなど): 賞味期限までまだ十分期間があっても、業界の慣習により販売期限が設定され、それを過ぎると廃棄対象となることがあります。
- 欠品への恐れ: 「お客様に迷惑をかけられない」という思いから、欠品を避けるために多めに在庫を抱え、結果として売れ残りを生むことがあります。
これらの背景を知ることで、私たち消費者が「てまえどり」を実践したり、「トクポチ」のようなフードロス削減通販を利用することの意義がより深く理解できます。
家庭でできる!簡単フードロス対策5選
フードロスを減らすために、今日から家庭で簡単に取り組める対策を5つご紹介します。
1. 「買う前」に冷蔵庫チェック&買い物メモ作成
最も基本的で効果的な対策です。買い物に行く前に必ず冷蔵庫や食品庫の中身を確認し、何がどれくらい残っているかを把握しましょう。その上で、必要なものだけをリストアップした買い物メモを作成します。これにより、無駄な買いすぎや二重買いを防ぐことができます。
ポイント:
- 冷蔵庫の中を見やすいように整理整頓しておく。
- 週に一度「冷蔵庫空っぽデー」を設けるのも効果的。
2. 食材を「使い切る」工夫とレシピ活用
購入した食材は、無駄なく最後まで使い切ることを意識しましょう。野菜の皮や芯、茎なども捨てずに料理に活用できるレシピがたくさんあります。例えば、大根の皮はきんぴらに、ブロッコリーの芯はスープや炒め物に使えます。また、残った料理は翌日のランチにしたり、別の料理にリメイクしたりするのも良いでしょう。
ポイント:
- 「食材使い切りレシピ」などで検索してみる。
- 少量残った野菜はまとめてスープやみそ汁の具にする。
3. 「適切な保存」で食材を長持ちさせる
食材は、それぞれの特性に合った方法で保存することで、鮮度を保ち長持ちさせることができます。例えば、葉物野菜は湿らせたキッチンペーパーで包んでポリ袋に入れ、立てて保存する。肉や魚は購入後すぐに使わない場合は小分けにして冷凍保存する、などです。食材の保存方法について一度調べてみることをおすすめします。
ポイント:
- 冷凍保存を積極的に活用する(日付を記入しておくと便利)。
- 開封後の乾物や調味料は密閉容器に移し替える。
4. 「食べきれる量」を意識して調理・注文する
料理を作る際は、家族の人数や食べる量を考慮し、食べきれる分だけを作るように心がけましょう。最初は少なめに作り、足りなければ追加するくらいの気持ちでいると、作りすぎを防げます。外食時も同様に、注文しすぎないように注意し、食べきれない場合は持ち帰りが可能かお店に確認してみましょう(衛生面に配慮し自己責任で)。
ポイント:
- 大皿料理ではなく、個別に盛り付けると量の調整がしやすい。
- 「あと一品」は、冷蔵庫にある残り物で簡単に作れるものにする。
5. 賞味期限と消費期限を「正しく理解」する
「賞味期限」は「おいしく食べられる期限」であり、この期限を過ぎてもすぐに食べられなくなるわけではありません。一方、「消費期限」は「安全に食べられる期限」なので、こちらは期限を守る必要があります。賞味期限切れの食品は、すぐに捨てずに見た目や匂いなどを確認し、まだ食べられるかどうかを自分で判断する習慣をつけましょう(ただし、判断は自己責任で行い、不安な場合は無理に食べないこと)。
ポイント:
- 期限表示が近いものから使うように、冷蔵庫内を整理する。
- 「トクポチ」のようなサイトでは、賞味期限が近い商品や、場合によっては切れた商品も扱っていますが、これは上記のような理解に基づいています。
まとめ:毎日の小さな意識がフードロスを減らす第一歩
フードロスは、私たちの日常のちょっとした行動や意識を変えることで、確実に減らしていくことができる問題です。今回ご紹介した5つの対策は、どれも今日からすぐに始められるものばかりです。
そして、「トクポチという通販サイトはあなたにもできるフードロス対策です。」という選択肢も、これらの家庭での取り組みを補完し、さらに効果的にフードロス削減に貢献する方法の一つです。無理なく、楽しみながら、地球にもお財布にも優しい生活を始めてみませんか?
前の記事では、日本のフードロス問題の現状と私たちにできることについて解説しました。
日本のフードロス問題の現状とは?私たちにできること
次の記事では、トクポチを利用することが、どのように具体的なフードロス削減アクションに繋がるのかを掘り下げます。
あなたもできる!フードロス削減アクション|トクポチなら手軽に貢献