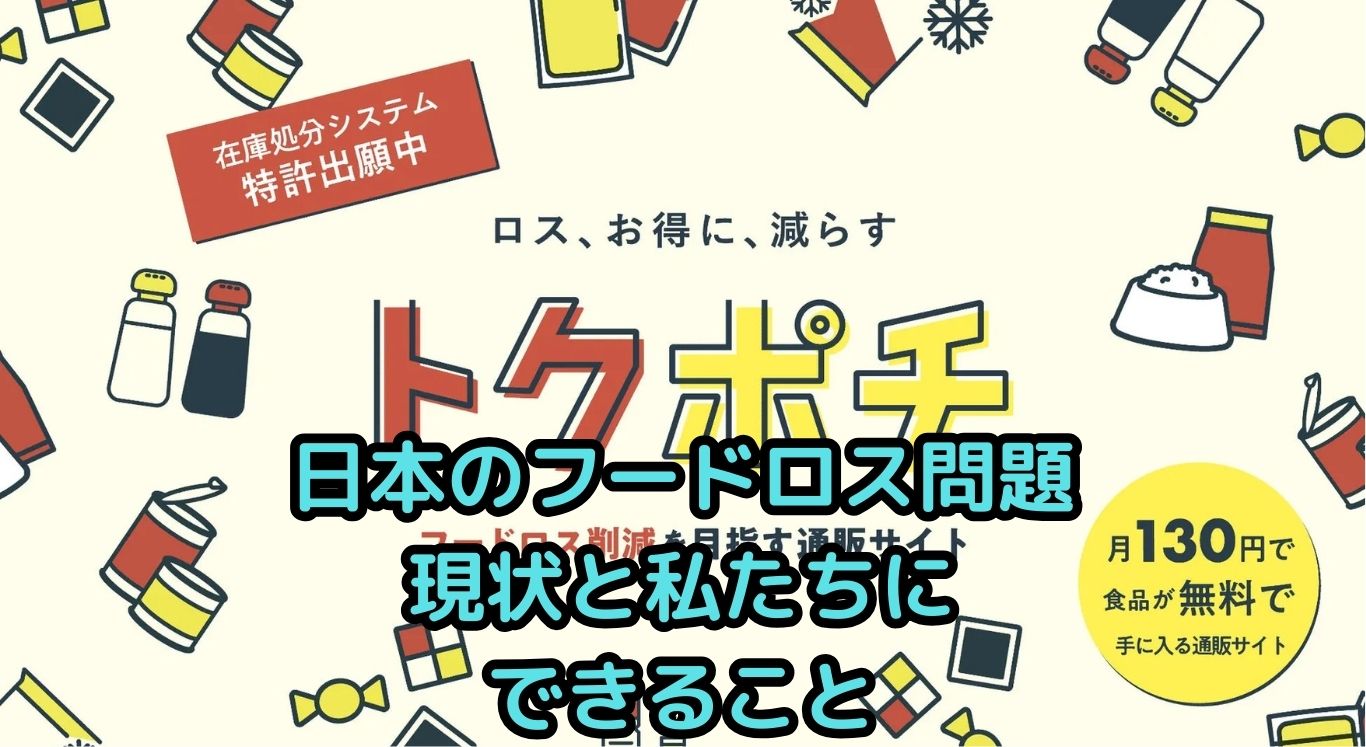「フードロス」という言葉を耳にする機会が増えましたが、日本のフードロス問題が実際にどれほど深刻なのか、そして私たち一人ひとりに何ができるのか、具体的にご存知でしょうか?
この記事では、日本のフードロス問題の現状を分かりやすく解説し、日常生活の中で私たちにもできる具体的なアクションをご紹介します。この問題を知ることで、「トクポチという通販サイトはあなたにもできるフードロス対策です。」という言葉の重みと、その行動の価値がより明確になるはずです。
日本のフードロス問題の現状:驚くべき量の食料が捨てられている
日本国内では、まだ十分に食べられるにも関わらず廃棄されてしまう食品、いわゆる「フードロス」が大量に発生しています。
農林水産省の推計によると、日本の食品ロス量は年間約522万トン(令和2年度)にものぼります。この量は、
- 国民一人ひとりが毎日お茶碗一杯分(約113g)のご飯を捨てているのとほぼ同じ量。
- 国連世界食糧計画(WFP)が世界中で行う食糧援助量(年間約420万トン)の約1.2倍。
つまり、日本は世界的に見ても非常に多くの食料を無駄にしている国の一つなのです。食べられるのに廃棄される食品が、毎日大型トラック約1,430台分にもなると言われています。
フードロスはどこで発生しているのか?
フードロスは、大きく分けて2つの発生源があります。
- 事業系食品ロス(約275万トン): 食品メーカー、卸売業者、小売業者、外食産業など、事業活動に伴って発生するロス。規格外品、返品、売れ残り、作りすぎなどが原因です。
- このうち、製品になってから捨てられている食品が約94万トン(食品メーカー25万トン、食品卸11万トン、小売店58万トン)。特に小売店の58万トンの多くはお惣菜などが占めています。
- トクポチが扱うような有名メーカーの商品は、滞留在庫としてフードロス予備軍となることが多いです。
- 製品になる前の原材料段階で捨てられる食品も約181万トンと非常に多く、例えば輸入果物が熟れすぎて廃棄されるケースなどがあります。
- 家庭系食品ロス(約247万トン): 一般家庭から発生するロス。食べ残し、手つかずの食品(直接廃棄)、皮のむきすぎなど(過剰除去)が原因です。
トクポチは、主に事業系食品ロスの中でも、特に「製品になってから捨てられる食品」や「滞留在庫」といった、まだ十分に価値のある商品に焦点を当てて取り組んでいます。
フードロスが引き起こす問題
大量のフードロスは、単に「もったいない」というだけでなく、様々な問題を引き起こします。
- 環境への負荷: 廃棄された食品を処理するために多くのエネルギーが使われ、CO2が排出されます。また、焼却処理による大気汚染や、埋め立てによる土壌汚染のリスクもあります。
- 経済的な損失: 食料生産にかかった資源(水、土地、労働力など)や費用が無駄になります。
- 食料需給の不均衡: 世界には飢餓に苦しむ人々がいる一方で、日本では大量の食料が捨てられているという倫理的な問題もはらんでいます。2050年には世界の人口が96億人に達し、現在の2.5倍にあたる20億人が飢餓に苦しむと予測されています。
なぜフードロスは発生するのか?主な原因
フードロスが発生する背景には、様々な要因が絡み合っています。
事業系の主な原因
- 「3分の1ルール」などの商習慣: 製造日から賞味期限までの期間を3等分し、最初の3分の1を過ぎた商品は小売店に納品しにくくなるという慣習。これにより、まだ賞味期限が十分に残っていても市場から外れてしまう商品が発生します。
- 過剰な生産・仕入れ: 需要予測の難しさや、欠品を恐れるあまりの過剰な生産・仕入れ。
- 規格外品: 形が悪い、大きさが不揃いといった理由で、品質には問題がなくても市場に出回らない商品。
- パッケージの印字ミスや破損: 中身は問題なくても、外装の不備で販売できなくなる商品。
- 季節限定品やイベント品の売れ残り。
家庭系の主な原因
- 買いすぎ: セールなどでつい買いすぎてしまい、使い切れずに賞味期限・消費期限が切れてしまう。
- 料理の作りすぎ・食べ残し。
- 冷蔵庫の中身を把握できていない: 奥の方で忘れ去られ、気づいた時には期限切れ。
- 賞味期限と消費期限の誤解: 賞味期限が切れたものをすぐに「食べられない」と判断してしまう。
- 不適切な保存方法による食品の傷み。
私たちにできること:身近なフードロス対策アクション
フードロス問題は深刻ですが、私たち一人ひとりが意識を変え、行動することで削減に貢献できます。
家庭でできること
- 買い物前に冷蔵庫をチェック: 在庫を確認し、必要なものだけを購入する「買いすぎない」意識が大切です。
- 「てまえどり」を実践: スーパーなどで商品を選ぶ際、棚の手前にある販売期限の近い商品から積極的に選ぶことで、お店の廃棄ロス削減に協力できます。
- 食材を使い切る工夫: 皮や芯なども料理に活用したり、残った料理はリメイクしたりと、食材を余さず使い切るレシピを試してみましょう。
- 適切な保存方法を心がける: 食材に合った保存方法で長持ちさせましょう。冷凍保存も有効です。
- 食べきれる量だけ調理する: 外食時も同様に、注文しすぎないように注意しましょう。
- 賞味期限と消費期限を正しく理解する: 賞味期限が過ぎてもすぐに捨てるのではなく、見た目や匂いで判断することも大切です(自己責任の範囲で)。
社会全体でできること・トクポチの活用
家庭での取り組みに加え、フードロス削減に取り組むサービスを積極的に利用することも有効なアクションです。
- フードロス削減通販サイトの利用: まさに「トクポチ」のようなサイトを利用することで、訳あり商品や賞味期限が近い商品を購入し、廃棄されるはずだった食品を救うことができます。これは、私たち消費者にとって手軽で、かつお得にフードロス対策ができる非常に有効な手段です。
- フードシェアリングサービスの活用: 余剰食品を必要とする人とマッチングするサービス。
- 食品ロス削減に取り組む飲食店を選ぶ。
- フードバンクへの寄付: まだ食べられるのに様々な理由で市場に出せない食品を、必要としている施設や人に届ける活動。
まとめ:小さな行動が大きな変化を生む
日本のフードロス問題は、私たちの想像以上に深刻な状況です。しかし、この問題は決して他人事ではなく、私たち一人ひとりの日々の選択や行動が大きく関わっています。
「買いすぎない」「作りすぎない」「食べ残さない」といった家庭での基本的な心がけに加え、「トクポチ」のようなフードロス削減に貢献できるサービスを賢く利用することは、誰にでもできる具体的なアクションです。「トクポチという通販サイトはあなたにもできるフードロス対策です。」この言葉をきっかけに、まずは身近なところからフードロス問題について考え、行動を始めてみませんか?
前の記事では、トクポチ利用者のリアルな口コミや評判をまとめました。
トクポチ利用者のリアルな口コミ・評判まとめ|お得感と満足度は?
次の記事では、フードロスがなぜ発生するのか、その原因と家庭でできる具体的な対策について、さらに詳しく掘り下げます。
フードロスはなぜ起こる?原因と家庭でできる簡単対策5選